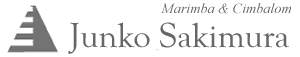ツィンバロン(Cimbalom)は、ハンガリーを中心とする中欧・東欧地域で見られる、台形の箱に張った金属製の弦を叩いたり弾いたりすることによって演奏する楽器。 ザックス=ホルンボステル1楽器分類コードは314.122-4,5で、共鳴箱付き板ツィター(314.122)に分類される。なお、チェンバロや初期のピアノも同族。
民族楽器として東欧に広く分布する他、ジョゼフ・シュンダによって改良されたコンサート・ツィンバロンが、ハンガリーを中心に分布する。コンサート・ツィンバロンは39コース以上の弦、4オクターブ以上の音域を持つ。
アルファベット表記では、Cimbalomの他に、cimbál, cymbalom, cymbalum, țambal, tsymbaly and tsimbl 、日本語では、ツィンバロン、チンバロン、ツィンバロムなどの表記も多く用いられる2。ロマの音楽で多く用いられる他、コダーイ、ストラヴィンスキー、クルターグ、ディティーユ、アンドリーセンなどの近現代の作曲家にもしばしば用いられている。コダーイがオペラから編んだ組曲『ハーリ・ヤーノシュ』(第3曲、第5曲でソロ的に扱われる)が特に有名で、しばしば演奏される。
歴史
記録に残された単純なバチを使うタイプのツィター族の楽器は、紀元前3500年のアッシリアのレリーフにみられる3以来、各地で様々なこの打弦楽器の発展を見ることになった。
これがヨーロッパに到達したのは大移住時代のことだ。最古の現存する図像はスペイン最北西端にあるSantiago de Compostela大聖堂にある1184年のものである415世紀には以下のように各地に広がって大変人気のある楽器になっていたことが伺える。
- 年代 場所 名称
- 1460年ごろ ボヘミアdulce melos
- 1461 イタリア dulcimelos, dulcemelos, salterio
- 1477 チューリヒ hackbrett
- 1499 フランス doucemer, tympanon
ただし、これらの楽器の調律システムはバラバラであった。
大きな変革がもたらされたのは18世紀に、ドイツのヴィルトゥオーゾ、Pantaleon Hebenstreit (1667 – 1750)によってであった。1697年にMerseburgにて、彼はガットと金属弦の二重弦を持った長さ2.7mもの大型の楽器を作り、ドレスデンの宮廷などで披露した。彼の演奏は大変な評判を呼んだ。1705年にはパリを訪れ、ルイ14世の前で御前演奏を行い、彼を大変感心させた。その結果、ルイ14世はその楽器に「パンテレオン(Panteleon)」という新しい名称を与えた5。18世紀の終わりにはイタリアのSalterio奏者Dall ‘Olioが、フル・クロマチックの楽器を製作した。
18~19世紀には、ロマにも採用され、各地で盛んに演奏されるようになった。1848年のハンガリー独立以降は、特に「ハンガリーの楽器」として、国のシンボルとして扱われるようになった。
ツィンバロンがクラシックで取り上げられるようになったのは、ハンガリーオペラの父、Ferenc Erkel のオペラ「Bánk bán (1861)」であると思われる。この作品の成功によって触発されたJoseph Schundaは、楽器の改良に取り組み、2オクターブ半だった音域を4オクターブ半まで広げ、ペダルを用いたダンパーシステムと脚をつけた。この「ハンガリー風ツィンバロム」が最初にお目見えしたのは1874年だった。Schundaはコンサート・ツィンバロンの生産をブダペスト・オペラの向かいのピアノ店で行った。この楽器は1878のパリ万国博覧会に出品されたことをきっかけに、ハンガリー国内で人気が高まり普及が進んだ。

これを更に改善したのがLajos Bohákで、1900年から彼の工房で生産をはじめた。現代使われるのは主にこのタイプの楽器である。Schundaが工房をおいていたハンガリーのOpera Zongorateremの他、スロバキアのBohak、チェコのVšianskýなどが主要なメーカーである。

ツィンバロンとピアノの関係
上記の通り、ツィンバロンは1700年代に大型のものが作られ、「パンタレオン」と呼ばれた。パンタレオンは当時のヨーロッパで流行したが、その奏法や特徴が黎明期のピアノ製作に多大な影響を与えたといわれる6。
ピアノのハンマーは、軸を支点に回転し打弦するが、これは既存の鍵盤楽器には見られなかった方式で、パンタレオンの奏法を参考にした可能性が高い。また、今日のピアノ・メーカーに直接つながる先駆者、ジルバーマンは、ダンパーを常時開放する装置を備えたピアノを製作したが、これはダンパーを持たないパンタレオンの響きを求めたものであった。やがてこの装置はピアノのペダルシステムへと発展する。なお、ベートーヴェンの「月光」ソナタの第1楽章は、このダンパーを持たない響きを求め、常時ダンパーを開放して弾くように指示している。これは、19世紀後半以降のピアノでは響が長くなり過ぎて不可能だが、ツィンバロンで弾くことで、当時ベートヴェンが想定した響きを思い浮かべることはできる。
ツィンバロンとチェンバロの関係
ツィンバロンの主要な奏法はバチで弦を叩くことであるが、弦を爪で弾くこともある。イタリア発祥したチェンバロ(Cembalo)の正式名称は Klavicembaloであり、Salterio (Cembalo = Cimbalom)に鍵盤(Klavi)を付けたものという意味であった。フランス語のClavecinも同様。
CLAVECIN, subst. masc
Étymol. et Hist. 1611 clavessins (Cotgr.); orth. reprise par Fur. 1690, Ac. 1694-1740 et Trév. 1704-71 (ce dernier dict. notant aussi la forme clavecin); 1680 clavecin (Rich.). Empr., avec apocope de la dernière syllabe, au lat. médiév.clavicymbalum de même sens, composé de clavis « clé » et de cymbalum « cymbale », attesté sous la forme clavicembalum en 1397, puis en 1404 sous la forme clavicymbalum par le poète allemand Eberhard von Cersne, Der Minne Regel ds Romania, t. 77, pp. 26-27, d’où le m. fr. clavycimbale, 1447 ds Gay.
ツィンバロンもチェンバロも共鳴箱付き板ツィターに分類される。
ツィンバロンの楽曲
日本ではマイナー楽器との印象が強いが、実はドビッシー、ストラヴィンスキーなど有名作曲家が曲を書いている楽器である。
- フランツ・リスト:「ハンガリー狂詩曲第3番」(ドップラーによる管弦楽版)
- ドビュッシー:「レントより遅く」(作曲者自身による室内オーケストラ版)
- ストラヴィンスキー:「狐」「ラグタイム」
- バルトーク:「ラプソディー第1番」
- コダーイ:組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
- デュティユー:「瞬間の神秘」「夢の樹」
- クルターグ:「クアジ・ウナ・ファンタジア」op.27「石碑」op.33
- アンドリーセン:「時間 (De Tijd)」
- コステロ:「イル・ソーニョ (IL SONGO)」
- ブーレーズ:「レポン (Repons)」
- ジョン・クーリッジ・アダムズ:「シェヘラザード.2」「もうひとりのマリアの福音書」
- レハール: 喜歌劇「ジプシーの恋」
- カールマーン: 喜歌劇「チャールダーシュ侯爵夫人」「伯爵夫人マリッツァ」
また、近年では、リストなどの、明らかにツィンバロンを想定しただろうと思われるパッセージを実際にツィンバロンを使って演奏する編曲も増えてきている。
脚注
- Hornbostel-Sachs
- ツィンバロムは日本打弦楽器協会推奨表記
- なお、これが実際に打つタイプなのか引っ掻くタイプなのかは実際にはよくわからない。引っ掻くタイプの方が有力。
- 出所:http://cimbalom.profitux.cz/ 。ただし、これも引っ掻いているのか打っているのかは分からない。
- David Charlton: Pantaleon Hebenstreit, http://www.classical.net/music/comp.lst/acc/hebenstreit.php (2017年12月6日取得)
- 当時の著名なオルガニスト、C.G Schröterによる。